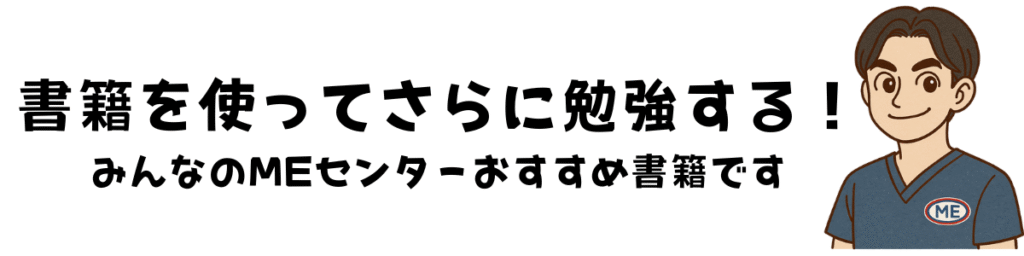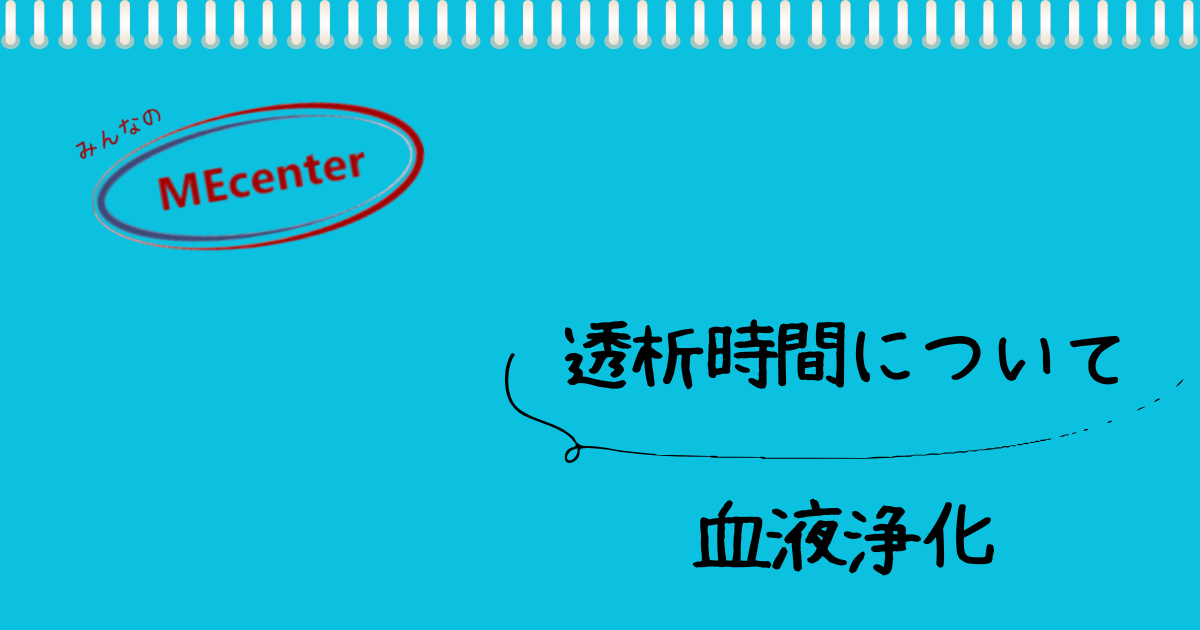透析室で新人として働き始めたあなたが、初めて透析患者の血液を操作している場面を想像してください。
週3回、1回4時間の透析を行う患者さんを前に、「なぜ4時間なのか」「もっと短くできないのか」と
疑問を持つことがあります。
患者さんから質問されると、慌てて答えに詰まってしまうこともあるでしょう。
この記事では、透析時間4時間の根拠と技士として知っておくべき調整ポイントがわかります。
- 透析時間4時間がKt/Vや中分子物質除去に基づく医学的根拠であること
- ダイアライザー性能・血流・透析液流量など技術的観点での調整方法
- 患者QOLと治療効果のバランスを考えた臨床工学技士としての判断軸
透析時間の理想と現実

まず、透析の目的を再確認しましょう。
慢性腎不全の患者さんでは、腎臓が老廃物の除去や電解質・水分バランスの調整機能を失っています。
そのため、血液透析が必要となります。
血液透析(HD)は、人工腎臓であるダイアライザーを通じてこれを補います。
しかし、腎臓が24時間365日働くのに対し、透析は週3回、各4時間程度。
1週間で換算すると血液をきれいにするための時間は通常168時間であるのに対し、
透析患者の場合は12時間程度しかないため、限られた時間で効率的に血液を浄化しなければなりません。
この効率性を測る指標として、Kt/Vがあります。

Kt/Vは「どれだけ血液が浄化されたか」を示し、
日本透析医学会のガイドラインでは1回あたり1.2以上が目標とされています。
4時間という時間設定は、この値を達成するための現実的な基準なのです。
- 透析治療は腎臓の代わりに血液をきれいにする
- 透析効率を表す指標としてKt/Vがある
- Kt/vの目標値は1.2以上
透析時間の理想値:HDPについて

そんな悩ましい透析量について評価する指標としてHDPというものが存在します。
HDP(Hemodialysis Product)は
1回の透析時間×週の透析回数×週の透析回数
で算出することができます。
ちなみに一般的な血液透析(1日4時間、週3回)のHDPは36となります。
つまり、維持透析患者の場合、HDP36以上を確保するのは最低限必要だということです。
このHDPは高いほど合併症のリスクが少なく、生命予後が改善されていると言われており、
推奨される値は70以上とされています。
ちなみに4時間透析と3時間透析を比較した場合、3時間透析の方が死亡率が2倍ほど死亡率が上昇すると
言われています。
- プラン1 長時間透析(1日8時間 週3回)
HDP=72 - プラン2 頻回透析 (1日3時間 週5回)
HDP=75
ではなぜHDPを70以上確保するような設定ではなく36以上でいいという判断になるのでしょうか?
ここからは、週3回4時間の設定がなぜ標準的な設定になったのかを考察していきます。
- HDPは透析量について評価する指標
- HDPは透析時間が重要視される
- HDPの目標値は70以上
4時間の医学的根拠:尿素除去と中分子物質
では、なぜ4時間なのか?
医学的には、尿素やクレアチニンといった低分子量物質の除去が一つの鍵です。
例えば、体重70kgの患者さんの体液量は約40Lと仮定します。
ダイアライザの尿素クリアランスが200mL/minの場合、Kt/V = (200 × 240) / 40,000 = 1.2となり、
ちょうど目標値を満たします。
これが4時間の根拠です。
しかし、低分子物質だけでなく中分子物質(例:β2-ミクログロブリン)の除去も重要だということ。
分子量が500~2000Da程度のこれらは、4時間程度の透析で効率的に除去され、
長期的な合併症(透析アミロイドーシスなど)の予防に寄与します。
短すぎると中分子除去が不十分になり、長すぎると患者負担が増すため、4時間がバランスポイントとされています。

技術的視点:ダイアライザーと血流・透析液流量
次に、技術的な側面を見ていきましょう。
透析時間の決定には、ダイアライザーの性能や血流・透析液流量が深く関わっています。
- ダイアライザーの性能
膜面積や材質がクリアランスに影響
現在の高性能ダイアライザーは、4時間で十分な浄化が可能に - 血流速度(QB)
通常200mL/minが標準
QBが低すぎると4時間でもKt/Vが不足する - 透析液流量(QD)
500mL/minが一般的で、これにより濃度勾配が維持され、効率的な物質移動が可能に
例えば、QBが200mL/minに落ちると、クリアランスが低下し、Kt/Vが1.2を下回るリスクがあります。
逆にQBを上げすぎると再循環が増え、効率が落ちることもあります。
技士として、患者さんの血管条件やシャントの状態を確認し、最適な設定を調整するスキルが求められます。

患者目線での4時間:QOLとのバランス
医学と技術だけでなく、患者さんの生活も考慮しなければなりません。
週3回×4時間は合計12時間/週。
これ以上長くなると、仕事や家庭生活に影響が出ます。
一方、短時間透析(例:2~3時間)は頻度を増やす必要があり、シャントへの負担やスケジュール調整が課題に。
4時間は、治療効果とQOLの妥協点として広く採用されているのです。
これはHDPにも関連しており、理想的なHDPにするためには患者さんの理解も必要だということです。
実際、患者さんから「もっと短くならない?」と聞かれることもあるでしょう。
そんなとき、4時間で透析に納得させることができる知識が技士には必要です。

- 4時間の医学的根拠は小分子量から中分子量までの体に不要な物質を6割以上除去できるから
- 血液量やダイアライザの性質でも透析効率を上げることができる
- 透析時間を上げると治療効果は上がるがQOLは低下する
透析時間を長く、頻回にできない理由:4時間以外の選択肢
では4時間透析以外にはどのような選択肢が摂られるのでしょうか?
Kt/Vの観点から考えるのか、HDPの観点から考えるのかで答えは異なりますが、
基本的に4時間以外の選択肢は以下の通りです。
- 短時間高効率透析:Kt/Vの観点から透析効率を上げる
高性能ダイアライザーを使い、QBを350mL/min以上に
3時間程度で済むが、シャントが強くないと難しい - 長時間透析:Kt/V、HDPの観点から透析時間を伸ばす
6~8時間実施する施設もあり、血圧安定やリン除去に優れるが、患者負担が大きい - 在宅透析(HHD):HDPの観点から透析時間、透析回数を伸ばす
自宅で頻回短時間や夜間長時間を行うケースも
ただし、患者さんの状態(残腎機能、体格、合併症)に応じた柔軟な対応を学ぶことが重要です。
例えば、Kt/Vが1.4以上必要な大柄な患者さんでは、そもそも透析時間が4時間では足りないこともあります。
ちなみに頻回に透析を行うことでHDPの値を大きくすることが可能では?という考えもあります。
理論上で言えば透析回数を頻回にすることで透析効率は上昇しますが、主に2つの障害がります。
- 現状の保険制度では月14回以上の透析は認められていない
- 在宅血液透析の導入リスク、費用が大きすぎる(透析を行うための改装工事や、高額な水道代)
結論、頻回透析はコスト上の問題で現実的ではないということです。
- 透析効率を上げるか長時間透析をすることで透析の治療効果を上げることができる
- 頻回透析は保険制度やコストの関係で難しい
臨床工学技士としての役割
最後に、臨床工学技士としての役割を考えてみましょう。
透析時間4時間の裏には、医学的根拠と技術の結晶がありますが、
それを患者さんに最適に届けるのは私たちの仕事です。
- モニタリング
透析中の血圧やシャント音をチェックし、異常を早期発見 - 調整
QBやUF(除水量)を微調整し、Kt/Vを目標に近づける - 教育
患者さんに「なぜ4時間か」をわかりやすく伝え、治療への理解を深めてもらう
未来に向けて、透析技術は進化を続けています。
ウェアラブル人工腎臓や再生医療が実用化されれば、4時間という基準も変わるかもしれません。
最新情報をキャッチアップし、柔軟に対応する姿勢が求められます。
まとめ
今回は透析時間についてまとめてきました。
今後保険の改正などで透析時間の常識が変化する可能性もありますが、
2024年度最新版では週3回4時間透析が基本です。
透析時間が4時間である理由は、Kt/Vに基づく浄化効率、中分子物質の除去、技術的限界、
患者QOLのバランスが絡み合った結果です。
4時間の裏にある医学と技術を理解し、日々の業務で「技士としての価値」を発揮してください!
一緒に頑張りましょう!